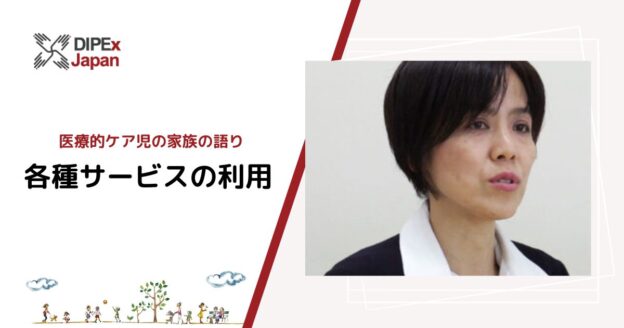まあゲームなんですけれど、ゲームとかもどんどん、どうやったら勝てるかとかって、こう追求していくんですね。
どのボタンを押したら何々、どのボタン押したらこうなるよとか、一切教えてなくて。
自分でパパパパパッて、覚えてやってくので、どんどんどんどん、上手になっていくんです。
何をやってるかはあまりよく分かってないんですけど、ゲームで、マリオのお金、取ってくるじゃないですか。
マリオじゃないんですけれど、それのはたから見たバージョンじゃなくて、自分が取っていく側になっていく、ミニオンズバージョンなんですけど、バナナを取っていくのとかなんですけど、それとかをすごく楽しんだりとか、今してます。
で、あと面白いのが、言葉もまだ足らないんですけれど、グーグルの音声検索ですね。
で、そこにポッとやってて、「ドラえもん、ドラえもん、ドラえもんのかばん」とか。
それが相手に伝わらなくて、「土曜日ですね」とか「今、分かりません」とか言って。
何かもう、いっぱいこう言われるんですけど。
親だったら、もう何回も聞かれて嫌だなとかって思うんだけれど、やっぱりあのAIさんたち、パソコンさんたちは、根気良くずっと、「ほにゃららですか。ほにゃららですか。分かりません」とか、そういうので何回も言うんですよ。
分かってもらえるために。そのしつこさって言ったらいけないんですけれど、すごくかわいくて。
それで、だんだんだんだん、滑舌も少しずつうまくなってきたっていうのは、現代のあるあるなのかなとか思いながらいます。
それで検索して、出てきたら、写真が、「ドラえもんのかばん」とか言うと、ドラえもんのかばん、いろいろ出てきて。
好きなのこうやってしながら、探したりとか。「これ欲しい」とか言って、「それは幼稚園の子たちが使うのだから駄目だよ」とかって言ったら、「そっか」とか言いながらとか。そういうのが今すごく楽しいやりとりです。