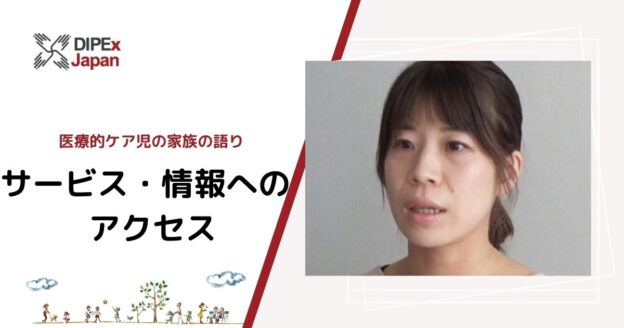――これまで利用していた以外のもので、こういうものを利用したいっていうようなご希望ありますか。
そうですね。もっと、人と触れ合う機会を増やしたいですし、成長を促す機会っていうのと、私がもう少し楽になれる機会っていうのも同時に欲しいですね。
訪問介護まではいかなくても、訪問看護のレスパイト事業や訪問型の児童発達支援だったり、そういうところも都内を中心にあるとは聞いているので、制度として使えたらいいのになっていうふうには思ってます。
――これまでその申請はされたんでしょうか。
申請はしてみたものの、娘の状態だと、娘は医療的ケアは必要ではあるけれども、介護が必要っていう認定は下りなくて、障害者手帳の申請も通らない。でも医療的ケアは必要っていうような状態で。
私の問い合わせた自治体の見解としては、そのようなお子さんは基本的には、就学までは親御さんが、主体的にケアをするっていう前提があるそうで、介護の認定もなく、障害者手帳もないお子さんで、児童発達支援の許可が下りた前例がないと言われて。
そもそも申請まで、こぎ着くことができなかったっていう感じです。
――そのときお母さんも、ちょっと悔しい思いというか、反論したい気持ちもあったと思うんですけど、そのとき何かおっしゃったんですか。
そうですね。
お子さんをいろいろ審査をされたりとかして、実際のうちの様子をよく分かった上で、もっと困ってる人がいるからちょっと難しいですって言われるんだったら、まだしも…。
前例がないからって言われたことに関しては、じゃあ前例って誰がつくるんだろうかとか…。
困っている、支援が必要だと思ってることは事実なのに、そこには、なかなか手が差し伸べられないんだな。じゃあ誰が助けてくれるんだろうかっていうような思いはあります。