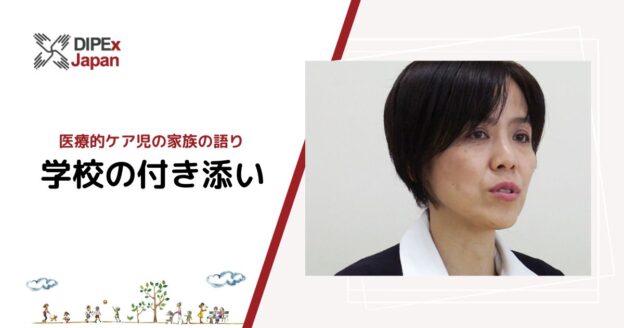嚥下(えんげ)の回復が少しずつうちの子始まっていって、吸引器が最初に(学校に)見学に行った頃は、24時間の吸引が必要でしたけど、入学の頃は24時間までいらないかもっていうふうになっていったんです。
ちょいちょい引かなきゃいけないけど、体勢によって何とかキープできる。
でも、吸引がいらなくなってくるっていうことは、じゃあ食べられるんじゃないのっていう。
食べることに関しても、私自身が栄養剤だけで育てていくっていうことに疑問を感じていたので、胃ろうから自分で作ったご飯をとにかく食べさせたかったんです。
自分でいろんな栄養を考えて、例えば便秘気味ってなったら繊維が多いものでとか。
繊維にも不溶性と水溶性があるとか、そういうのを調べながらこの子のより良い状態をつくっていきたいっていうのがすごくあったので、そこは病院のほうとも相談しながら、力を入れていた部分だったんですね。
嚥下の回復のためのリハビリも、病院のPT(理学療法士)さん、OT(作業療法士)さんと相談しながらずっと進めてきたし、その努力があってとは言わないけれど、きっと本人の成長で回復が進んだんだろうなとは思ってますけど。
そのことで逆に学校に入学したときは、栄養剤の注入しか学校は認めていなかったので、胃ろうから注入をしてました。
病院側はもうこれならある程度の形態の食事だったら口から行ってもいいよっていうOKサインがお医者さんからもリハの先生たちからも出たけど、どうしても学校がうんって言わない。
そこに安全があるのか、その責任は誰が取るのかみたいなところで、うまくそこが進まなくて。
結局2年生までは、ほとんど付き添いで登校して、その理由が給食みたいな。
給食を(学校で)出してもらえないので私がお弁当を作って、ちょっと柔らかめの軟飯とか軟菜を作って持っていって食べさせ方も自分で安全確認しながらで。
それをどれだけ先生に伝えていっても先生はなかなか怖いので、受け入れてもらえないみたいな感じの時期だったかな。