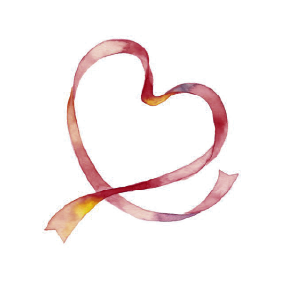インタビュー時年齢43歳(2022年4月)
障害の内容:聴覚障害(軽度難聴)、肢体不自由(右手首の障害・機能全廃)
障害をもった年齢:軽度難聴は27歳から始まり、現在右耳はほとんど聞こえない。右手首は40歳
現在の状況:企業の産業看護師
北陸地方在住の女性。妊娠中にストレス性難聴になり徐々に右耳はほとんど聞こえなくなった。
また、3年前にスキーで右手首に怪我をし、治療をしたが、全く使えなくなってしまった。
聞こえについては会議や右側から話しかけられると聞こえづらく、右手首については重い扉を開けにくいといった不便さがある。
産業看護師として、社員の健康管理やメンタルケア、復職支援などを行っている。
プロフィール詳細
総合病院で3年働いたあと、27歳で結婚を機に臨床を離れて企業の看護師になった。
企業の看護師は基本的に一人職場で周囲に相談できる人がいない状態で、そのタイミングで妊娠したこともあって、ストレス性の難聴になった。
妊娠中でステロイドを使うことが出来ず、その後難聴が進んで、結局右耳はほとんど聞こえない状態になっている。
就職当初は聞こえていたため、周囲から聞こえないことについて理解を得にくく、周囲の対応から嫌な思いをすることもあった。
また3年前に、スキーの事故で右手首を怪我してそれ以降たびたび手術を受けている。だが思ったようには良くならず、TFCC損傷という手首をひねる動作ができなくなる状態になり、手首にある月状骨がつぶれて壊死するキーベック病にもなった。合計8回の手術を繰り返したが、5回目くらいからは後遺症が残るかもしれないと告げられた。
そんななか、職場にいるときに心筋梗塞を起こした人がいて、看護師である自分がその場で心臓マッサージをしたことで、その人は一命をとりとめた。
しかし、心臓マッサージでは手首に強い負荷がかかり、マッサージの最中に靭帯が切れるような音がして、状態が悪化してしまった。
整形外科の主治医には優先すべきは自分だと言われたが、看護職である自分がその場でマッサージをしないという選択肢はなく、後悔はしていなかった。
だが、自分を犠牲にして人の命を救ったことについて、看護師だから応急処置は当然という周囲の反応があり、褒めて欲しいわけではなかったものの、やる気が削がれてしまって、1年前に職場を変えた。
今後手首に後遺症が残るだろうということもあり、転職のタイミングで主治医から、身体障害者手帳の取得を勧められた。
最初は自分が手帳を取得することに抵抗があったが、後からでは取得しにくくなる可能性があるとも言われ1年ほどかけて相談をして、右関節機能障害全廃で4級の手帳を取得した。
また同じタイミングで、難聴に関しても混合性難聴による聴力障害で6級の手帳を取得した。
現在、手首については、重い引き戸を開けにくいことや、パソコンのマウスを扱いにくい、血圧測定の際にマンシェット(腕に巻き付ける部分)をスムーズに巻けないなど、日常での困り事が多い。
だが片手のみの障害なので、周囲には伝わりづらい。
例えば車椅子の人が職場にいたら扉をスライドドアに変えるなどの環境調整が職場に求められるが、障害が片手だけだとそういうこともない。
障害が軽いと思われがちだが、障害に大小や軽い重いはなく、どんな障害でもその本人には不便であり、他の人には痛みは分からないと思ってしまう。
また難聴に関しては、以前はそれほど強く意識していなかったが、ここ2年のコロナ禍で日常的にマスクを付けるようになり、店のカウンターなどのビニールカーテンによって聞こえないことでの不便さを強く感じるようになった。
集合形式の会議は聞こえないこともあり、その中で発言を求められることで、非常に緊張度が高くなる。
聞こえないということは周囲には伝えているが、なかなか理解してもらうことは難しく、見えない障害の難しさを感じてきた。
その一方で、コロナ禍のためにチャット機能の活用やWeb会議で録画して後から確認することもできて、それは非常に助かっている。
2年前に、自分が治っていかないことや、痛いことを隠さずにいられる空間が欲しいと思い、それまでとは別のアカウントを取って、SNSで手首の障害や痛みについて発信をし始めた。
そのことで同じような障害を持つ人と繋がり、話をとことん聞いてもらったことで、話を聞くことの重要性に気づいたように思う。
それ以前は、看護職として人に関わる際、日々の業務の中で相手のことを分かっているように思ってしまっていたが、障害をもって以降は、まずは相手の話を聴こうという姿勢になった。
今は自分にしかできない仕事があるように思い、「聞いて」というサインを出している人と、時間をかけて向き合うようにしている。
障害をもったことで、人間性を成長させてもらったようにも感じている。
医療現場では、看護職だから障害に理解があるわけではなく、むしろ看護職だから理解しようとしていなかったり、看護職が同じ看護職に対して、心無い言葉を発したりすることがあって、自分自身も、障害をもってから気づいたことが多い。
また、病院に行ったときにビニールカーテンで聞こえないことが多いなど、社会での生きづらさを感じた。
いわゆる臨床現場では、障害のある看護職が働くことが難しいのは残念で、都会ではできても地方で難しいと感じることも多いが、障害のある看護師がいろいろな働き方ができるようになったら良いと思う。
これから看護師を目指す人には、障害を隠さずに周囲に助けを求めて、自分だからできることを探しながら、看護師になる夢を諦めないで欲しい。
自分自身も障害を持ったことで、一緒にチェアスキーなどを楽しむ障害のある友達が増えており、障害のあるなしに関わらず一緒に楽しめるような社会や環境作りが、今後は求められると感じている。
企業の看護師は基本的に一人職場で周囲に相談できる人がいない状態で、そのタイミングで妊娠したこともあって、ストレス性の難聴になった。
妊娠中でステロイドを使うことが出来ず、その後難聴が進んで、結局右耳はほとんど聞こえない状態になっている。
就職当初は聞こえていたため、周囲から聞こえないことについて理解を得にくく、周囲の対応から嫌な思いをすることもあった。
また3年前に、スキーの事故で右手首を怪我してそれ以降たびたび手術を受けている。だが思ったようには良くならず、TFCC損傷という手首をひねる動作ができなくなる状態になり、手首にある月状骨がつぶれて壊死するキーベック病にもなった。合計8回の手術を繰り返したが、5回目くらいからは後遺症が残るかもしれないと告げられた。
そんななか、職場にいるときに心筋梗塞を起こした人がいて、看護師である自分がその場で心臓マッサージをしたことで、その人は一命をとりとめた。
しかし、心臓マッサージでは手首に強い負荷がかかり、マッサージの最中に靭帯が切れるような音がして、状態が悪化してしまった。
整形外科の主治医には優先すべきは自分だと言われたが、看護職である自分がその場でマッサージをしないという選択肢はなく、後悔はしていなかった。
だが、自分を犠牲にして人の命を救ったことについて、看護師だから応急処置は当然という周囲の反応があり、褒めて欲しいわけではなかったものの、やる気が削がれてしまって、1年前に職場を変えた。
今後手首に後遺症が残るだろうということもあり、転職のタイミングで主治医から、身体障害者手帳の取得を勧められた。
最初は自分が手帳を取得することに抵抗があったが、後からでは取得しにくくなる可能性があるとも言われ1年ほどかけて相談をして、右関節機能障害全廃で4級の手帳を取得した。
また同じタイミングで、難聴に関しても混合性難聴による聴力障害で6級の手帳を取得した。
現在、手首については、重い引き戸を開けにくいことや、パソコンのマウスを扱いにくい、血圧測定の際にマンシェット(腕に巻き付ける部分)をスムーズに巻けないなど、日常での困り事が多い。
だが片手のみの障害なので、周囲には伝わりづらい。
例えば車椅子の人が職場にいたら扉をスライドドアに変えるなどの環境調整が職場に求められるが、障害が片手だけだとそういうこともない。
障害が軽いと思われがちだが、障害に大小や軽い重いはなく、どんな障害でもその本人には不便であり、他の人には痛みは分からないと思ってしまう。
また難聴に関しては、以前はそれほど強く意識していなかったが、ここ2年のコロナ禍で日常的にマスクを付けるようになり、店のカウンターなどのビニールカーテンによって聞こえないことでの不便さを強く感じるようになった。
集合形式の会議は聞こえないこともあり、その中で発言を求められることで、非常に緊張度が高くなる。
聞こえないということは周囲には伝えているが、なかなか理解してもらうことは難しく、見えない障害の難しさを感じてきた。
その一方で、コロナ禍のためにチャット機能の活用やWeb会議で録画して後から確認することもできて、それは非常に助かっている。
2年前に、自分が治っていかないことや、痛いことを隠さずにいられる空間が欲しいと思い、それまでとは別のアカウントを取って、SNSで手首の障害や痛みについて発信をし始めた。
そのことで同じような障害を持つ人と繋がり、話をとことん聞いてもらったことで、話を聞くことの重要性に気づいたように思う。
それ以前は、看護職として人に関わる際、日々の業務の中で相手のことを分かっているように思ってしまっていたが、障害をもって以降は、まずは相手の話を聴こうという姿勢になった。
今は自分にしかできない仕事があるように思い、「聞いて」というサインを出している人と、時間をかけて向き合うようにしている。
障害をもったことで、人間性を成長させてもらったようにも感じている。
医療現場では、看護職だから障害に理解があるわけではなく、むしろ看護職だから理解しようとしていなかったり、看護職が同じ看護職に対して、心無い言葉を発したりすることがあって、自分自身も、障害をもってから気づいたことが多い。
また、病院に行ったときにビニールカーテンで聞こえないことが多いなど、社会での生きづらさを感じた。
いわゆる臨床現場では、障害のある看護職が働くことが難しいのは残念で、都会ではできても地方で難しいと感じることも多いが、障害のある看護師がいろいろな働き方ができるようになったら良いと思う。
これから看護師を目指す人には、障害を隠さずに周囲に助けを求めて、自分だからできることを探しながら、看護師になる夢を諦めないで欲しい。
自分自身も障害を持ったことで、一緒にチェアスキーなどを楽しむ障害のある友達が増えており、障害のあるなしに関わらず一緒に楽しめるような社会や環境作りが、今後は求められると感じている。