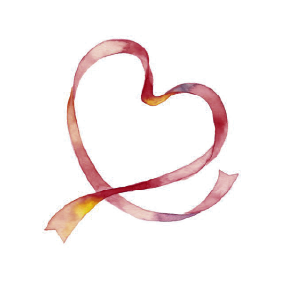インタビュー時年齢30歳(2022年4月)
障害の内容:高次脳機能障害、目の障害(下斜筋の麻痺、複視と斜位)
診断された年齢:18歳
男性。18歳に交通事故に遭い、高次脳機能障害と診断された。
大学を休学して1年後に復学したが、物が覚えられず、座学や演習には時間がかかった。
また、相手の感情を察することができないためコミュニケーションが難しく、3年次の実習で単位を落として1年間休学。再実習を経て卒業し、看護師免許を取得。
回復期病院で1年間の勤務を経て大学院に進学した。
プロフィール詳細
18歳で交通事故に遭い、手足や肋骨を骨折し、20日間ほど意識不明の状態で、入院中に高次脳機能障害と言われた。
事故後、滑舌が悪くなり、話すのがゆっくりになったのを自覚するようになった。
またその後は高次脳機能障害の症状として、音に敏感になり、視覚的にも、車のライトや人の貧乏揺すりなど細かい動きが煩わしく、イライラして怒りやすくなることや、イレギュラーなことに対応できずにパニックになるなど、事故前にはなかった症状に気づくようになった。
事故後から日記をつけており、それが自分の症状を振り返ったり、思いを発散したりするのに役立っていた。
事故後1年の休学を経て、ものを覚えにくく、座学は人より時間をかけて頑張って学んだ。
また看護技術も、友人に付き合ってもらい、放課後や場合によっては土日に練習を繰り返して習得した。
そのように知識や技術は時間をかけることでなんとかなったが、3年生の後半から長期の実習が始まった際、患者さんとコミュニケーションが取れなかったり、実習先の施設の騒音がうるさくてパニックになってしまったりすることがあり、2つの場所の実習の単位が取れなかった。
教員からは「看護はできない」と言われ、福祉系の学科へ方向転換を勧められたが、一度休学して1年後に看護の実習を行うことにした。
休学中は住み込みでアルバイトをしたが、バイト先には本当に様々な人がいて、その人たちと一緒に過ごしコミュニケーションをとるうち、それが自信になり、イレギュラーなことにも対応できるようになった。
復学後の実習に関しては、症状が軽い患者さんを担当させてもらうなどの配慮などもあって単位を取得することができた。
4年生では、看護師にはなれないと教員に言われていたため、行政保健師を目指して就職活動をしていたが、座学の試験は通るものの、面接が難しく就職先がなかなか決まらなかった。
病院では働けないと思っていたが、結局1カ所、中規模病院から内定が出たので、4月からはそこに勤めるつもりでいた。
しかし、3月の入職前研修の際に看護の手技が自分には難しくてパニックになり、そこで初めて職場に高次脳機能障害のことを伝えたら、解雇されてしまった。
その後、ナースセンター(看護師のための職業紹介所)から回復期病院を紹介されて、4月にそこに就職をした。
入職時に看護部長には自分の障害のことを伝えたが、配属先の師長にどこまで伝わっていたかは分からない。業務は日常生活援助が主だったが、生活リズムが乱れることが辛く、夜勤は1年間でトータル10回くらいしか入らなかった。
だが、先輩たちに看護技術を粘り強く教えてもらうような配慮もあって、働き続けられた。
そんな中、秋頃に、他の病院と合同の研修で会った人に大学院を薦められた。
職場では、それなりに自分が働けることも分かってきていたが、今の職場で10年後、20年後務めていることが想定できなかったので、3月末で退職し、現在は大学院生として学んでいる。
在職中、色々困ることはあったが、患者さんと話をするのは好きだった。
自分も18歳で事故に遭い、それまでできていたことができなくなったという経験があり、できるようになることの喜びもよく分かったので、回復期病院にいる患者さんの気持ちは分かるように感じていた。
障害を理由に何かを諦めるということは、周囲から言われてすることではないと思っており、周囲の人にできないという選択をさせられるのは、おかしいと思う。
周りには、本人ができないことではなく、できることを考えて欲しいし、これからの人には、まずは(自分がやりたいと思うことを)やりたいことをやってほしいと思う。
事故後、滑舌が悪くなり、話すのがゆっくりになったのを自覚するようになった。
またその後は高次脳機能障害の症状として、音に敏感になり、視覚的にも、車のライトや人の貧乏揺すりなど細かい動きが煩わしく、イライラして怒りやすくなることや、イレギュラーなことに対応できずにパニックになるなど、事故前にはなかった症状に気づくようになった。
事故後から日記をつけており、それが自分の症状を振り返ったり、思いを発散したりするのに役立っていた。
事故後1年の休学を経て、ものを覚えにくく、座学は人より時間をかけて頑張って学んだ。
また看護技術も、友人に付き合ってもらい、放課後や場合によっては土日に練習を繰り返して習得した。
そのように知識や技術は時間をかけることでなんとかなったが、3年生の後半から長期の実習が始まった際、患者さんとコミュニケーションが取れなかったり、実習先の施設の騒音がうるさくてパニックになってしまったりすることがあり、2つの場所の実習の単位が取れなかった。
教員からは「看護はできない」と言われ、福祉系の学科へ方向転換を勧められたが、一度休学して1年後に看護の実習を行うことにした。
休学中は住み込みでアルバイトをしたが、バイト先には本当に様々な人がいて、その人たちと一緒に過ごしコミュニケーションをとるうち、それが自信になり、イレギュラーなことにも対応できるようになった。
復学後の実習に関しては、症状が軽い患者さんを担当させてもらうなどの配慮などもあって単位を取得することができた。
4年生では、看護師にはなれないと教員に言われていたため、行政保健師を目指して就職活動をしていたが、座学の試験は通るものの、面接が難しく就職先がなかなか決まらなかった。
病院では働けないと思っていたが、結局1カ所、中規模病院から内定が出たので、4月からはそこに勤めるつもりでいた。
しかし、3月の入職前研修の際に看護の手技が自分には難しくてパニックになり、そこで初めて職場に高次脳機能障害のことを伝えたら、解雇されてしまった。
その後、ナースセンター(看護師のための職業紹介所)から回復期病院を紹介されて、4月にそこに就職をした。
入職時に看護部長には自分の障害のことを伝えたが、配属先の師長にどこまで伝わっていたかは分からない。業務は日常生活援助が主だったが、生活リズムが乱れることが辛く、夜勤は1年間でトータル10回くらいしか入らなかった。
だが、先輩たちに看護技術を粘り強く教えてもらうような配慮もあって、働き続けられた。
そんな中、秋頃に、他の病院と合同の研修で会った人に大学院を薦められた。
職場では、それなりに自分が働けることも分かってきていたが、今の職場で10年後、20年後務めていることが想定できなかったので、3月末で退職し、現在は大学院生として学んでいる。
在職中、色々困ることはあったが、患者さんと話をするのは好きだった。
自分も18歳で事故に遭い、それまでできていたことができなくなったという経験があり、できるようになることの喜びもよく分かったので、回復期病院にいる患者さんの気持ちは分かるように感じていた。
障害を理由に何かを諦めるということは、周囲から言われてすることではないと思っており、周囲の人にできないという選択をさせられるのは、おかしいと思う。
周りには、本人ができないことではなく、できることを考えて欲しいし、これからの人には、まずは(自分がやりたいと思うことを)やりたいことをやってほしいと思う。
インタビュー11体験談一覧
- もともと協調性もあり、人と関わる仕事がしたいと看護師を選んだ。特別看護にこだわりがあるわけではなかった(テキストのみ)
- 採用担当者には障害を伝えていたが、我慢するかどうかは自分が決めることなので一緒に働く同僚には伝えなかった(テキストのみ)
- 入職前の実技研修でパニックになり、その時に障害のことを伝えたら予告解雇を言い渡されて違う職場を探した(テキストのみ)
- 自分の考えをまとめて話すのが苦手だったが、3,4行の日記をつけ始め読み返すことで気づくことがあり役だった(テキストのみ)
- 教員に免許が取れても看護師は難しいだろうと言われ、行政保健師の就職活動をたくさん受けたが面接で苦戦した(テキストのみ)
- 全体を統括する看護部長に伝えて、直属の師長には言わなかったが、誰にどこまで伝わっているかは問題だと思う(テキストのみ)
- ある領域の実習では比較的症状が軽い人や意思疎通のとりやすい人の担当にしてもらい、それは配慮だったように思う(テキストのみ)