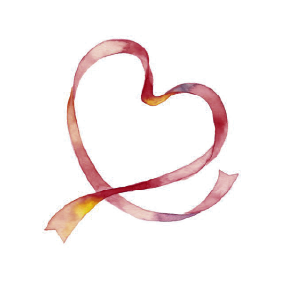※写真をクリックすると、動画の再生が始まります。
インタビュー時年齢58歳(2022年3月)
障害の内容:PDD-NOS(特定不能の広汎性発達障害)
診断された年齢:47歳
関東地方在住の男性。40代でうつ病と糖尿病の教育入院のために入院していた先で発達障害と診断された。
その病院には社会人の看護学生が実習に来ており、その学生を見て、自分も看護師になることを決め、退院後に看護大学に入学して看護師の資格を取得。
新卒で高齢者の療養施設に就職をしたが、コミュニケーションがうまくいかないと言われ、1年強で退職をして、現在は翻訳活動をしている。
語りの内容
2回精神科に入院してるので、精神科出身の看護師としてもやって(みたかったし)。
あとで文献を調べたら統合失調症を克服して看護師になられた方の文献があって。その方は同じ病をもつ仲間を見る看護師としてのプライドっていう立派なことを書かれてて。
そこまで私は立派な人間ではないんですけども、でもやっぱり、自分の2回の入院で一番癒やしになったのは、同じうつ病の患者さん仲間との雑談だったので。
その同じ苦しみや、内容とか程度は違いますけれども、いくら看護師さんがすごくいい看護をしてくれても、なんか伝わりきらないところがあって。
伝わりきれないっていうか、癒やされきれない。
それなのに、例えば患者さん同士のテーブルでの午後の語り合いとかカウンセリングなんかで一緒に離婚の話とか、それぞれ会社を辞めた話とかで泣くんですけど、それはすごいカタルシスになるんですよね。
そういう作業療法とか、カウンセリングとか、精神的な病院で1990年代にはそれ(ケア)を受けるっていう幸運があって。そういう経験も活かしたかったんですね。
製薬の研究所とかあるいは、高校、大学時代って、自分より頭のいい人はいっぱいいたので、しかも(自分は)人生うまくいっていないから、自分は知能指数が非常に高いっていうことは全然自覚なかったんですよね。自尊心もないというか。ただ(社会人で看護師を目指して学んでいる人がいると)聞いてひょっとすると、看護学科の受験はうまくいくだろうと。
看護学校で習うそのいろいろな疾患の基礎知識はあるので、それはすごい楽だろうなと。それから真面目な話をすると、
製薬、薬のいいところ、悪いところって、製薬の研究者って言っても、私の場合は実験係なので、まだ研究者という肩書まで至らなかったんですけども
会社での研究者っていうのは課長さん以上なので、自分は実験工員さんだったんですけどね。
でもその薬の開発の経緯とか、薬のいろいろいいところ、悪いところを、製薬出身としても、患者としても、看護に生かせるんじゃないかと。