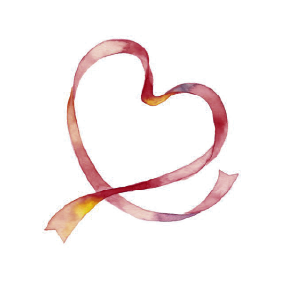学校・職場での障害の開示
障害のある人が自分のことを周囲にどこまで伝えるかは様々です。
まず外から見えない障害は理解されにくく、周囲の共感や協力を得るのが難しいことがあります。
障害が外から見える場合でも、社会が障害のある人を前提としていないので、社会的不利や不公平を一番強く感じているのは障害のある人自身です。
障害があることを伝えた結果、不当な扱いを受けて悔しい思いをした人もいれば、障害があることを隠して頑張った人もいます。
事実をありのままに伝えて就職し、周囲の仲間に支えられた体験を話した人々もいますし、疾病や障害を持つことで見えてくる世界が必ずしも負の側面ばかりでないことに気づいた人々など、様々な体験が語られています。
これらの語りの中から、障害の有無に関わる欠格条項の見直し、バリアフリー社会の実現に向けて、どのような取り組みが必要であるかを考えてみたいと思います。
伝えない理由
一般的に、自分の障害や病いを周囲に伝えることは、進学や雇用などで不利になる可能性を考えて躊躇してしまうことがあります。障害はプライバシーで、伝えない自由があります。また自分で伝える必要を感じていても、言ってみないと結果は分かりません。インタビューを受けた人は、障害を伝えない理由や、伝えることを躊躇する思いについて話していました。
外から見えづらい聴覚障害のある人は、どう伝えるかは自分次第だと思いながらも、自分のマイナス面を表に出すことに勇気が要ると話していました。
またベーチェット病と診断されている人も、就職時の健康診断などから病気自体を隠すことができないが、自分で伝えても理解してもらえない経験や誤解されたことがあったという話をしていました。
障害名が一般的によく知られているものかどうかは、伝えることに影響しそうです。線維筋痛症の人は就職時に職場へ病気のことを伝えようと思いましたが、あまり知られていない病名のために、伝えることで自分がどのように見られるのか不安を抱いたという話をしていました。
また集団生活においては、少数派の人に対して、多数派の人の行動や意見に合わせるよう暗黙のうちに強制する無言の圧力が働きがちです。少数派の人もまた同じように扱ってほしいという思いがあるかもしれません。インタビューに答えた人たちからは、特別扱いされると困るなど、周囲と同じように扱って欲しいという思いが聞かれました。
看護師の仕事をしばらく中断した後、精神障害と発達障害の診断を受けて、訪問看護師として仕事に復帰した人は、急に休むこともないと思ったので予め伝えることはしなかったと話しています。
同じく他の人と違う扱いを受けたくなかったと話す内部障害の人は、友人や学校には透析を受けていることを伝えていたが、実習の際に実習先の指導者などに伝えなかった思いを次のように話しています。
さらに線維筋痛症の人も、診断名を伝えることで自分が希望しなくても何か制限されてしまい、他の人と違う扱いを受けるのではないかということを懸念していました。
特に配慮が必要ないので伝える必要がなかったという人もいますが、伝えても解決しないという思いや、周囲からの反応を懸念して伝えなかったと話した人がいました。高次脳機能障害の人は、自分が我慢すれば良いという思いを話していました。
医療現場で伝えること
日本の医療職の法律には、国連から廃止を勧告されている欠格条項がいまだ残されています。欠格条項とは、障害のために資格取得を制限することを定めた法律等の条文です。表立って差別をすることは現在禁止されていますが、それでも医療者の法律に相対的な欠格条項が残されていることは、医療者は障害がないことが前提だという雰囲気を作り続けていると言われてきました。
また近年欧米を中心に、健常者を前提としている文化や制度、規定などが、障害のある人が医療者になることを阻んできたことが問題視されています。例えば医学部や医療系学部の教育方針に障害のある人を排除するような文言がないか教育機関は見直しを迫られています。
しかし、このような取り組みはまだ始まったばかりです。依然として障害がないことが前提となっている医療現場で、障害のことを他者に伝えることは一般的にハードルが高いことです。また医療者自身のなかに一定の疾患や障害のある人に対する偏見があることも、分かっています。
このようななか、差別や偏見を恐れたり、実際に誤解されたりした経験があるために、医療現場で自分の障害を伝えづらいと思っていた人がいました。
精神障害と発達障害があると診断された人は、看護職として働いているときに障害名を人に伝えたことで過小評価された経験があり、その後も、周囲に自分のことを伝えづらかったと話していました。
40年以上前の話ですが、1型糖尿病の人は看護学校へ入学した際に、自分の主治医から病気のことを学校の教員には言わない方が良いと言われた体験を話していました。
伝えたことがきっかけの離職
自分の障害を伝えるかどうか迷う理由の1つにどのような対応をされるのかが不安だという話がありますが、実際に障害を伝えたことによってそれが結果的には離職につながったことを話した人がいました。
次の精神障害と発達障害の人は、発達障害のことを伝えて就職した先で、うつ傾向があることを伝えた時に聞いていないという反応をされたことを話していました。
主治医から障害を伝えたら落とされるだろうと言われて、自分もそう思っていたため就職の面接の時には高次脳機能障害であることを伝えずに内定をもらっていた人は、入職前の実技研修のタイミングで伝えざるを得ない状況になり、結果的に職を失うことになってしまいました。
自分の勤務していた大学病院でベーチェット病であることが分かった人は、教授である主治医から自分の患者さんを預けられないと言われ離職した体験を話していました。
伝えるか否かをどう決めたか
伝えるかどうか、どう伝えるかに関しては正解がありませんが、インタビューで話した人たちは自分の障害を周囲に伝えるかどうかを決めるのに影響したものなどについて話していました。
例えば、身体障害者手帳を取得したことにより気持ちの変化があり、手帳を見せるわけではなくても自分の聞こえづらさについて周囲に伝えやすくなったと話す聴覚障害の人がいました。
自分自身が医療者を目指して学んでいる、もしくは医療者として働いている環境では、当然周囲にも医療系の人が多くいます。周囲に基本的な知識があることが伝えやすさに影響したと話した人がいました。
次のクローン病の人は、大学の時は周囲が医療系の学生なので、開示するのにハードルが低く、説明の仕方も自分の経験を伝えていたと話をしていました。
腎不全で人工透析をしていた人も、高校の時と違って医療系の短大へ進学してからは周囲が医療者を目指す人達で知識もあり、様々なサポートを得た体験を話していました。
また障害は必ずしも就職時から固定されているとは限らず、途中で障害をもつことになったり、場合によっては進行するものや変動がある場合もあります。入職していたときは聞こえていたが途中で難聴になった人は、聞こえにくくなったことを話したが、以前は聞こえていたので周囲に理解してもらえなかったことを話していました。
伝えて良かったこと
周囲に自分の障害を伝えることはハードルが高いことですが、伝えたことによって理解を得られたり、サポートされたり、反対に周囲にいる同僚の医療者が、その人から学ぶ機会が生まれたりすることもあります。
入職時に聞こえていて途中で聞こえなくなった場合に周囲に伝えても理解を得にくかったと話していた聴覚障害の産業看護師の人は、転職した際には最初に、片耳が聞こえにくいことを周囲に伝えました。その結果、聞こえていなさそうだったら肩を叩いてくれるなど、スムーズに仕事ができていることを話していました。
また次の内部障害の人は、それまでの経験上隠しきれないと思って入学時に友人に伝えたところ、様々なサポートを得ることができたことを話しています。周囲からあまり心配されたくないために最初にまとめて説明し、様々な症状があるが心配ないというところまで一連の流れで伝えていました。
また1型糖尿病の人は、低血糖で体調が悪いときには周囲に助けてもらったり、逆に周囲が自分の体験から学ぶようなこともあったため、病気を開示していて良かったと話していました。
幼い頃から自己免疫疾患だった人は、看護師になるための学校入学時に自分の病気を伝えた際、面接官に「患者の気持ちが分かるから君は向いている」と背中を押されるようなコメントをもらい、その言葉が自信になったというエピソードを話していました。
伝えることの必要性
外見で障害があることが分かったとしても具体的に何が出来て何が出来ないのかは、やはり本人に聞かないと分からないことが多くあります。肢体不自由で車椅子を使用している人は、所属部署を変わった時の体験から、いくら外見で分かりやすくてもきちんと説明する必要性を話していました。
2025年3月公開
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。

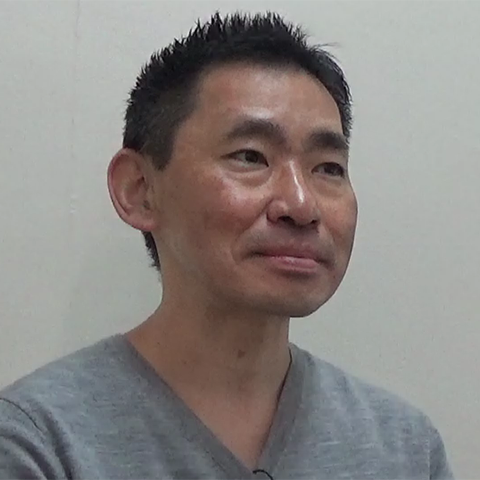 入試の面接では伝えていたが、実習先の指導者に伝えるかと聞かれたときは他の学生と違う対応をされるのも嫌だったので断った
入試の面接では伝えていたが、実習先の指導者に伝えるかと聞かれたときは他の学生と違う対応をされるのも嫌だったので断った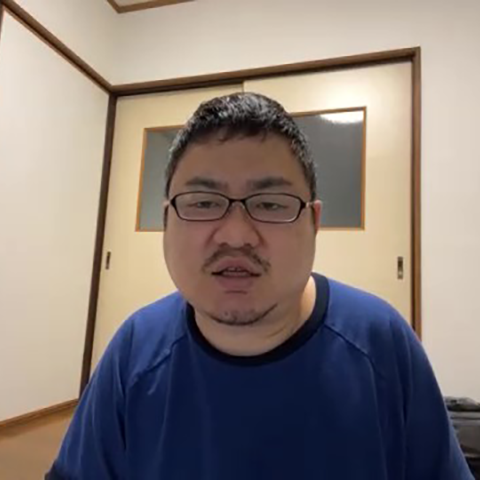 障害名や薬、症状について伝えただけで過小評価された経験もあり、周囲に自分から病気のことは伝えづらかった
障害名や薬、症状について伝えただけで過小評価された経験もあり、周囲に自分から病気のことは伝えづらかった 40年前の入学時、主治医から病気は黙っとけと言われ学校には言わなかった。自分も医療者が一番差別をしているように感じていた
40年前の入学時、主治医から病気は黙っとけと言われ学校には言わなかった。自分も医療者が一番差別をしているように感じていた 大学は医療系だったので周囲は病気の知識も持っており、病気のことは看護師になろうと思った動機と一緒に自然に話せていた
大学は医療系だったので周囲は病気の知識も持っており、病気のことは看護師になろうと思った動機と一緒に自然に話せていた これまでの経験上、隠しきれないので入学当初に周囲に伝えたところ、心配してくれて、様々な面でサポートをしてもらった
これまでの経験上、隠しきれないので入学当初に周囲に伝えたところ、心配してくれて、様々な面でサポートをしてもらった 前の病棟はストレッチャーの搬送を自然に代ってくれたが、病棟が変わった時何も言わずにいたら、できないの?と言われた
前の病棟はストレッチャーの搬送を自然に代ってくれたが、病棟が変わった時何も言わずにいたら、できないの?と言われた