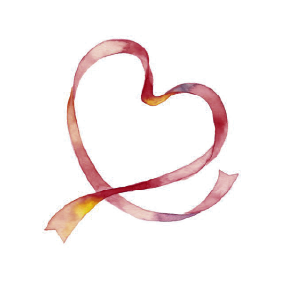学生時代の環境調整や配慮
日本では2016年に障害者差別解消法が施行されて、国公立の学校では障害のある人に対する合理的配慮の提供が義務になりました。また2024年4月に改正障害者差別解消法が施行されたことで、それまで努力義務だった私立の学校も含め全教育機関において、障害のある人が求めた場合の合理的配慮の提供が義務になっています。
しかし実際に教育現場で行われていることは、法律で定められた合理的配慮だけではありません。いわゆる「教育的配慮」と言われる各教員の工夫などは、昔から障害だけでなく困りごとがある学生に対して行われてきており、障害学生支援は法律で定められた合理的配慮と、教員が個人の采配で行う教育的配慮の組み合わせという考え方もあります。看護学生の時にすでに障害があった人たちは、配慮にまつわる多様な体験を話していました。
学校への配慮申請や相談のタイミング
近年、障害学生支援部署や相談窓口がある学校は増えていますが、支援体制には学校間格差もあると言われています。障害のある看護学生が相談をする窓口も様々で、相談をしてもその後の手続きが決められていない学校もあるようです。
幼少期に自己免疫疾患と診断されている内部障害の人は、入学当初に学生課に提出した診断書が教員側に共有されていなかった経験を話していました。
また発達障害のある人は、実習先でうまくいかなくなったタイミングで障害のことを教員に伝えた際、配慮を求めたわけではなかったが、逆にほかの学生には求められないような不公平な対応をされたと話していました。
どのような配慮が妥当なのかについては、学校側が答えを持っているわけではありません。配慮内容はいつも本人のニーズを確認しながら個別的に調整をしていくものです。聴覚障害のある人は、1,2年生の時の実習はとにかく行ってみて大学と一緒に自分に合った方法を探すといった経験を話していました。
この聴覚障害のある人は、大学側の教員には配慮内容に関してしっかり話し合いの機会をもらったという話をしていました。「障害学生の語り」の映像をご覧ください 。
具体的な配慮の例
法律で定められた合理的配慮は、個別のニーズにそっていることや、事業(教育現場なら学び)の本質を変えないことなどいくつかの条件があります。インタビューが行われたのは改正障害者差別解消法が施行になる前ですが、義務化になる以前からそれぞれの現場では様々な形で障害のある人への配慮が行われていました。
補助機器の使用
障害者支援や、障害学生支援の分野でも補助技術(Assistive Technology: AT)は目覚ましい進化を遂げています。医療現場でも、必ずしも障害のある医療者を想定して作られたものではありませんが、波形が目で見えるデジタル聴診器など、様々な補助技術が用いられています。
聴覚障害のある人は音量が大きくなる機械式の聴診器を使用していましたが、本人がそれを使うだけでなく、大学が次に入ってくる人も使用できるようにしてくれた話をしていました。一人の学生がいることで教育現場に起きた変化や得た知恵をいかに次に活かすかは、学校の重要な役割と言えます。
出席日数への配慮
慢性疾患などの内部障害がある場合、特定の曜日に定期的に診察や治療を受けることがあります。多くの学校では1週間単位で時間割ができているため、受診等で同じ曜日に欠席をすると特定の科目のみ欠席が増えてしまいます。このような時は、欠席を「公欠扱い」にするなど必要な配慮がなされます。しかし、座学では認められた公欠扱いが、実習では認められなかったことを話していた人がいました。
また公欠扱いにしてもらうために提出した診断書の共有がされておらず単位を落としかけたが、最終的には公欠扱いになったと話していた自己免疫疾患と診断されている内部障害の人もいました。
障害のある学生がいることを想定されていないカリキュラムの作りやルールは、障害のある学生が学ぶ上での社会的バリアになりえます。そのような慣習やルールをどのように見直していくかが今後教育現場に求められています。
同じく内部障害で通院が必要だったこの人は、欠席しても単位が認められるという配慮を得ていましたが、欠席分の課題は自分で補う形だったようです。
補助者の配置
一般の大学でもノートテイクや生活介助など、特定の役割を果たす補助者が学習支援に入ることはよくあります。インタビューに答えた人の中でも、補助者をつけて実習していた人がいました。
肢体不自由で車椅子を使用している人は、実習の時に専属の教員がついて自分ができない看護技術を補う形で実習を行ったと話していました。
障害のある本人も、初めて看護を学ぶので、どのような学習方法なのかはわかりません。そのためどんな配慮が自分に必要なのか分からないことが多くあります。調整や配慮の内容の決定プロセスは試行錯誤の連続で、そこには対話が欠かせません。
学校側は一度決めたので変えないということではなく、本人の意向を聞きながら、配慮や調整の内容をその都度見直して改善していく姿勢が求められます。
聴覚障害のある人は、座学ではノートテイクに入ってもらい、その後は実習中も含めて手話通訳にも入ってもらったという体験を話していました。また語りからは、医療系の科目に介助者が入る場合、介助者が専門用語を扱えるかどうかも本人の学習に影響することが分かります。
見学実習への代替
実際に患者さんと直接かかわる実習が難しい場合、見学という手段の変更を行って実習を行うことがあります。免疫抑制剤を使用している内部障害のある人は、特定の実習のみ見学に代替したことを話していました。
担当患者の調整
医療機関における看護系の実習では通常、一人の患者を受け持ってその人に必要な看護を考え実践していくという学習方法がとられます。担当患者さんは、看護学生が学習のために受け持つことを承諾された方になりますが、その中でも、学生に障害があっても学びやすい特性の方を教員が選択することがあります。
聴覚障害の人は、比較的声が聞きやすい患者を担当させてもらったことを話していました。この人の語りからは、教育現場の調整は障害に対応して決まったものはなく、現場での提案や本人の工夫を重ねながらより良い形を模索していくものであることが伺えます。
「配慮」という言葉は、相手に悟られずに行うといったニュアンスがありますが、法律で定められている障害のある人への「合理的配慮」は、障害のある本人の意向を出発点として、本人とそれを提供する事業者側との丁寧な対話が欠かせません。しかし実際には、本人抜きで勝手に配慮が行われてしまう場合もあるのかもしれません。
高次脳機能障害のある人は、明確に学校側から配慮内容を伝えられたわけではないが、振り返ると担当患者に関して配慮があったと思われることを話していました。
特に配慮はなかった
日本学生支援機構が毎年行っている「障害のある学生の修学支援に関する実態調査」では、大学が把握している障害学生数のうち何らかの支援(配慮)を受けている支援学生数の割合は、54.6%です(2022年度調査のデータ)。インタビューを受けた人たちのなかでも、障害があっても特に配慮はなかったという方々がいました。
配慮がなかった人の中には、配慮が必要なかった人もいますが、逆に必要な配慮が得られなかった人もいます。両者は見かけ上区別がつきにくいですが、海外では必要な配慮を受けられなかった医療系学生は必要な配慮を受けられた人に比べて成績が低かったという研究結果もあり、障害のある学生が必要な配慮を得て、障害のない学生と同等のスタートラインに立った上で学べる体制づくりが求められます。
配慮は必要なかった
幼少期から痛みがあり大学在学中に線維筋痛症と診断された人は、学校には伝えていたが他の人と同じように扱ってほしいという思いがあり、特に配慮の希望はしておらず、具体的な環境調整などもなかったことを話しています。
必要な配慮が得られなかった
看護学生が行う実習は一般的に元気な人でもとても大変だと言われます。自己免疫疾患と診断されている内部障害の人は、座学の授業では通院で休むことに対して出席の配慮が行われていたが、実習ではそのような配慮が認められなかった体験を話していました。
座学で配慮をしても実習では配慮をしないという方針の教育機関は多くあります。しかし、看護を学び看護職になる人の働き方は、非常に多様です。条件の厳しい出席日数を満たすことが看護の実習上の本質なのかどうか、多様性が重要とされる社会で問われているかものしれません。
2025年3月公開
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。

 障害のことは入学当初大学に診断書を提出して伝えた。しかしそれが共有されておらず、出席に対する配慮がなく単位を落としかけた
障害のことは入学当初大学に診断書を提出して伝えた。しかしそれが共有されておらず、出席に対する配慮がなく単位を落としかけた 実習でうまくいかず広汎性発達障害であることを伝えたら、自分だけ実習後に大学へ帰って報告を求められ、アンフェアだと思った
実習でうまくいかず広汎性発達障害であることを伝えたら、自分だけ実習後に大学へ帰って報告を求められ、アンフェアだと思った 本格的な実習は3年生からなので1,2年の実習はとにかく現場に出てみて、自分に合った方法を探るという目的もあった(手話)
本格的な実習は3年生からなので1,2年の実習はとにかく現場に出てみて、自分に合った方法を探るという目的もあった(手話) 聴診器は音が大きくなる電子聴診器を使用していたが、それは大学が購入してくれて次の学生も活用できる体制を作ってくれた
聴診器は音が大きくなる電子聴診器を使用していたが、それは大学が購入してくれて次の学生も活用できる体制を作ってくれた 実習中は一人専属の教員についてもらい、患者のおむつ交換や全身清拭、移乗など、自分ができないケアを補助してもらっていた
実習中は一人専属の教員についてもらい、患者のおむつ交換や全身清拭、移乗など、自分ができないケアを補助してもらっていた