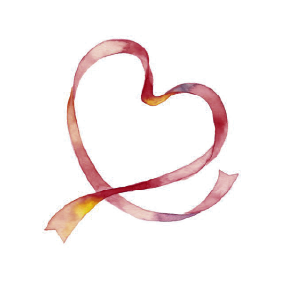※写真をクリックすると、動画の再生が始まります。
インタビュー時年齢58歳(2022年3月)
障害の内容:PDD-NOS(特定不能の広汎性発達障害)
診断された年齢:47歳
関東地方在住の男性。40代でうつ病と糖尿病の教育入院のために入院していた先で発達障害と診断された。
その病院には社会人の看護学生が実習に来ており、その学生を見て、自分も看護師になることを決め、退院後に看護大学に入学して看護師の資格を取得。
新卒で高齢者の療養施設に就職をしたが、コミュニケーションがうまくいかないと言われ、1年強で退職をして、現在は翻訳活動をしている。
語りの内容
実習のときに、どうもコミュニケーションがうまくいかないっていうよりかは、その状況全体がうまくいかなくなってしまったことがありまして。
だから広汎性発達障害を伝えたほうが話が進むかなと思って、実習のときに相談した(あるいは相談しなかった)「領域」っていうのは、例えば小児看護とか急性期看護とか慢性期看護とか、幾つか(実習の)「領域」が分かれるんですけれども、母性看護とか、産科、婦人科、母性看護ですけれども。
幾つかのうち三つでは、(自分の障害を教員に)開示したんですね。そのうち一つでは、例えば実習に付き合ってくださる先生が、僕のほうから、すみません、ちょっと障害があって余計なご負担をおかけしてって言ったら、いや、大丈夫です、私たちはプロですから、任せてください、謝らないでくださいって言う。超かっこいいとかって思ったんですけども。あの、それは美しい話で。
逆に私が開示したら、翌日先生が休まれてしまったというケースが(2回)あって(本人補足:どうしたらよいか分からず戸惑って休まれたのだと思う)。これは結構ショッキング。もしもっと早く、まあ…そうですね。
あとネガティブな経験としては、開示したら結局実習中に、2日にいっぺんは、いったんその実習先の施設からキャンパスに戻って、キャンパスで夕方――先生方も大変だったと思うんですけども――その領域の実習に関わる先生が約10人ぐらいいらして。その10人の先生方の前で私が1人で、その日の報告というか、反省というか(することになった)。
ちょっと理由は分からないんですけれども、私が想像するのは、例えば、施設で何かインシデント、アクシデントがありはしないかとか、そういうことを、何て言うのかな、話し合うことになったのかなとは思うんですけれども。
ただ2日にいっぺん、みんなほかの学生がもう施設から直接自宅に帰って、その日のレポートとか記録とかを書くんですけれども、僕はキャンパスに戻って1時間、ロスタイムになるわけですよね。先生も残業代が出たのかどうかはよく分からないですけど。
今は障害者も法律でもって、そういう特別扱いっていうか、健常な学生にしないことを障害学生に要求したら法律違反になる可能性が高いんですけども、まだその法律が施行される前、もう法律として将来こういうのができますよっていうことは先生もご存じだったとは思うんですけれども、施行前だったので、まあ法律違反にはならないと。
ただ大学っていうところですから、そういうことをするのがフェアなのか、アンフェアな、アンフェアっていうか、ファウルなのかっていう判断を先生はなさらないのかなって。