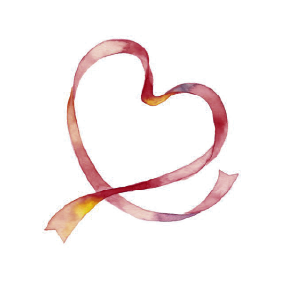※写真をクリックすると、動画の再生が始まります。
インタビュー時年齢:25歳(2018年12月)
障害の内容:聴覚障害(ろう)
学校と専攻:大学・看護学(2011年度入学)、大学院(2015年度入学)
関東地方在住の女性。生まれつきのろうで、両親もろうの家に育った。中学2年生の時に看護師になりたいと思い、看護大学に進学した。大学では、ノートテイクや手話通訳のサポートを得ながら講義や演習、実習をこなし、看護師の国家資格を得た。その後大学院に進学し、ろうの利用者が集まる施設で看護職として働いたり、ろう団体から依頼されて講演活動などをしている。
語りの内容
1年の最初に、大学院生に一緒に授業に入ってもらいノートテイクで情報収集をして助けてもらいました。その次にそれだけでは足りないので手話通訳を依頼して。手話通訳もいろんなところに依頼をしました。
看護師と手話通訳士を持っている方だと、看護の専門の知識を持っていて、また病院の中で注意しなきゃいけないこと、例えば予防面とか衛生面とか、どこを触っちゃいけないみたいなところも分かっている方だったので、とてもスムーズにいきました。
看護師ではないけれども幅広く活動されている方、手話通訳の方でもいろいろ依頼をしました。またパソコンを持ってきてもらって病院の中で持ち歩くのもできないので、ノートテイクか手話通訳のどちらかを使って勉強しました。手話通訳の場合だと、看護師資格を持っている、持っていない、さまざまなんですが、とにかくいろんな方法で1~2年のときは試しに実習をこなしました。
その結果、自分にとってはやっぱり看護師資格を持っている手話通訳というのがベストだな、専門用語とか薬剤の名前等も、言葉をきちっと理解して伝えてくれる通訳なので、例えば、咳嗽(がいそう)っていう言葉、せきですけど、専門的には咳嗽っていいますよね。
NGチューブとか、普通の通訳で医療用語が分からない場合には表現できないけれども、言葉の意味が何かって、看護師の人だと分かっているので、咳嗽っていう言葉を聞いたら、せきって手話で表現したりNGチューブと言えば、その胃管というのも手話で表してくれる。なので、とても分かりやすく伝わってきました。
3年生の半年間は、看護師資格を持つ通訳に来てもらって、ずっと一緒に実習をしました、という経過です。