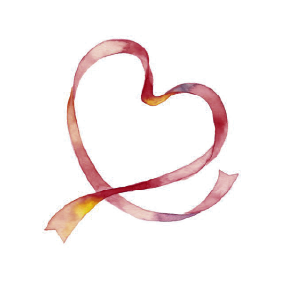※写真をクリックすると、動画の再生が始まります。
インタビュー時年齢:29歳(2020年11月)
障害の内容:聴覚障害(難聴)・内部障害(慢性腎不全)
学校と専攻:大学・看護学(2012年度入学)
関東地方出身の女性。中3の時に鼻咽頭がんになり、化学療法の副作用で難聴と慢性腎不全になった。通信制の高校で学びながら腹膜透析の治療を5年ほど続けて、腎移植を受けた。入院中、気にかけてくれた看護師のことが印象的で、自分の経験を役に立てたいとも思って、高校卒業後に3年間の療養期間を経て、看護系の大学に進学し、その後看護師として就職して現在4年目になる。
語りの内容
看護学生になると聴診器を購入して、聴診器を使用して、学内での練習をしたり実習にも行くんですけれども、聴診器だとやっぱり聞こえがちょっと良くなくて、あまりはっきり聞こえなかったので、先生に相談したところ、音量を上げられる聴診器があるんですね。
電池を入れて機械式になっていて、自分で音量の上げ下げができる聴診器があるんですけれども、それを大学側が、大学費として購入をしてくださって、それを貸し出ししてくださって、実習中だったりとか練習ではそちらを活用して。
実は難聴がある看護学生が初めてだったみたいなんですけど、そういうようなサポートをしてくださって、逆に私のような難聴がある方が次回入ってきた人のために、いろいろと聴診器に関しても、次回も活用できるようにっていうことをしてくださいました。
聴診器に関しては、大学で入学したらみんな統一の聴診器を大学の最初の費用に入ってる大学だったので、おんなじ聴診器をみんな配ってくださるというか、事前に購入をしてるようなところなんですけど、多分提携してる会社のほうに大学側が相談したところ、こういう聴診器もありますよっていうのでいろいろと見てくださって、その中で音量の上げ下げができるのがいいんじゃないかっていうことで、大学側で調べて購入してくださったんですね。
インタビュー19体験談一覧
- 低音が聞きにくいため教員がはっきりしゃべってくれる女性の患者さんを選んでくれた。他にもシャワー介助での工夫などがあった
- 退院後に外来通院を始めた高校生の頃、入院中に親身に話を聞いてくれた看護師に憧れを抱き、恩返ししたいと思うようにもなった
- 聴診器は音が大きくなる電子聴診器を使用していたが、それは大学が購入してくれて次の学生も活用できる体制を作ってくれた
- 特定の日の欠席が多くなることは、必要な治療ということで単位を認定された。欠席分に関しては教員に質問できる体制があった
- 実習に際して定められたワクチン接種ができない状態だったので、小児看護の実習だけは患者さんに触れない見学実習になった
- 自分のできないことが気になり落ち込んだ時、精神科の患者さんとかかわり、相手のできることを見つける精神科看護に関心を持った
- 実習が印象深く、就職先に精神科を選んだ。教員に相談してゆったり落ち着いて働ける場所を教えてもらいインターンシップに行った
- 就職活動の書類に健康状態を尋ねる書類があって驚いたが、担任と相談し、面接では4年間やり遂げたことを伝えることにした
- 入職後、直属の上司に難聴と体力のことを伝えた。夜勤は少しずつ様子をみてしんどかったらその都度相談してほしいと言われた