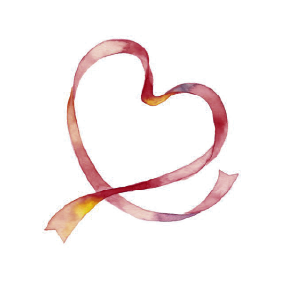障害があり看護を学ぶということ
看護職の業務を定めている「保健師助産師看護師法」には、いまも障害にかかる相対的な欠格条項が残されています。一方で、実際には障害があり看護職を目指して学んでいる看護学生は多くいます。障害をもちながら看護を学び、医療職を目指す人はどんな苦労があり、どういった工夫を行っているでしょうか。また自身のもつ障害が看護学生として学んだこととどのように関連するか、さまざまな人の体験を紹介します。
障害に関連して苦労したこと
こんにち障害は、その人本人の機能障害と、多数派向けにできている社会とのミスマッチによって生じるという「社会モデル」の考え方が主流です。この考えからすると、障害のある看護学生が直面する困りごとは、多数派向けにできている教育現場の文化やルールが、少数派である障害のある看護学生に合わないために生じているのかもしれません。そうだとしたら、改めてそうした文化やルールを見直す必要がありそうです。
障害のない学生にとっても医療現場での実習は大変です。実習中は睡眠時間や食事を削ることがあたりまえになっており、周囲は睡眠を削ったり食事をあまり摂らなくても大丈夫と言っていたが、難病のある自分にとって、それらによる疲労の蓄積が非常につらかったという話をしていた方がいました。
臨床現場での実習は緊張感を伴います。医療現場は、患者の命を預かる場であるため一定の緊張感は必要ですが、学生が委縮するような環境が健全な教育環境なのか、それは問いなおす必要があるかもしれません。また通常1-2週間で実習の場所や人間関係が次々変わる実習の方法も、障害のことを理解してもらうことに障壁になっているようです。
緊張すると吃音が出やすい症状のある人は、実習のできごとを次のように話していました。
様々な学生が看護を学ぶ時代においては、学習環境やその方略が「一律」であることで、学びにくさを感じる人もいます。精神障害と発達障害の診断があり、人の話を聴く時すごく集中しいないと聴けず、長時間になると頭も痛くなってとにかく疲れやすい症状があるという人は、大学院生時代にグループワークについて、みんなと一緒に学ぶことの難しさを感じていました。
自分なりの工夫
障害がありながら看護を学ぶ学生だった方々は、様々な壁を感じながらも自分なりの工夫を積み重ねていました。聴覚障害がある人は実習で、一人で立ち上がらないよう依頼したことが担当患者に伝わっておらず、その患者が一人で立ち上がろうとしていることを手話通訳に教えてもらって気づいたというヒヤリとした経験があり、その後は何度も確認するようになったと話していました。
実習中のストレスマネジメントはどの学生にとっても大きな課題ですが、その方法は人それぞれです。一般的に実習中はアルバイトをしないという人が多いですが、クローン病の人は、実習中もアルバイトを行うという別の日常があることの大切さを話していました。
高校を卒業した後の学生生活は、友人関係や生活範囲が広がるため、病気のことを知っている家族以外と食事をとる機会も増えます。看護学生になってからクローン病と診断された人は、外ではみんなと同じように食事をして翌日以降に調整を行っていた工夫を話していました。
また事故で高次脳機能障害と診断された人は、事故の後から日記をつけるようになったことが良い結果につながったのではないかという話をしていました。
休学の経験
学生生活は一度入学したらそのまま学び続けることが多いですが、場合によっては途中で一度学ぶことを休む選択も可能です。慢性疾患のある人は、治療を続けながら実習を行うことは難しいと考え休学を選択したときの思いを話していました。
自信を持てた出来事
インタビューで話した人たちは、障害をもちながら看護を学ぶ過程において、多数派仕様の教育現場の壁もあり、迷いや不安を感じていた人が多くいました。しかしそのなかでも自信を持てるようになった出来事について話をした人たちがいます。
看護大学に入ってからクローン病と診断された人は、陸上部の部活やアルバイトを通じて少しずつ自信を取り戻していったことを話していました。
また実習中に体調を崩してしまった内部障害と聴覚障害のある人は、実習で患者さんとかかわるうちに自分が役立てることがあるのではないかと思えるようになったことを話していました。
自分の障害と関連のある学び
インタビューでは、実習で患者さんとの関係性が難しかったが、試行錯誤した結果喜んでもらえたことが印象に残っているといった話や、勉強はとても大変だったけれど「何とかやれている」という感覚で自分としては頑張って勉強していたと話した人がいました。このように、障害の有無にかかわらず、看護学生時代には様々な学びがありそれぞれに印象的な出来事があるものです。
そのなかでも障害をもちながら看護を学ぶ人の中には、障害があったゆえに、自分の障害と関連したその人ならではの学びを経験していた人がいました。
在学中にクローン病と診断された人は、自分の経験からクローン病の人の運動習慣を知りたいと思って卒業研究に取り組んだことを話していました。
また在学中に事故で脊髄損傷になり車椅子を使うようになった人は、同じく自分の経験から、脊髄損傷の方々を対象に卒業研究に取り組んだことを話していました。
ページのトップで触れた保健師助産師看護師法における障害にかかる欠格条項ですが、これは医師法に準じて書かれており、「心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」には、「免許を与えないことがある」とあり、厚生労働省令には、「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする」とあります。
障害者欠格条項をなくす会の調査によると、実際には欠格条項に該当する人全員に免許が交付されていますし、ここで語った人たちは様々な障害をもちながら一人ひとりが多様な学びをしていることが分かります。この欠格条項のためにいまだに障害のある人が看護職になれないと思われていることは大きな問題です。
2025年3月公開
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。

 実習は睡眠時間を絶対に削られるような状態だった。立ちっぱなしであることより帰宅後にやることが多くストレスだった
実習は睡眠時間を絶対に削られるような状態だった。立ちっぱなしであることより帰宅後にやることが多くストレスだった 緊張で看護師への報告で言葉が出ず、外見で吃音はわからないので大変だった。病棟を次々変わるので自分のことは説明していない
緊張で看護師への報告で言葉が出ず、外見で吃音はわからないので大変だった。病棟を次々変わるので自分のことは説明していない 患者の安全を守れないかもしれないという体験をして悩んだ後、何度も確認をしたり立ち位置を工夫するようになった(手話)
患者の安全を守れないかもしれないという体験をして悩んだ後、何度も確認をしたり立ち位置を工夫するようになった(手話) 実習中は体力的にバイトを控えたほうが良いという意見もあったが、自分はそれがあることでストレスが抜けていたので続けていた
実習中は体力的にバイトを控えたほうが良いという意見もあったが、自分はそれがあることでストレスが抜けていたので続けていた 学生時代は周りと一緒にたらふく食べたり飲んだりしていた。もちろんお腹を下すが、翌日は控えるなど数日間の中で調整をしていた
学生時代は周りと一緒にたらふく食べたり飲んだりしていた。もちろんお腹を下すが、翌日は控えるなど数日間の中で調整をしていた 自分のできないことが気になり落ち込んだ時、精神科の患者さんとかかわり、相手のできることを見つける精神科看護に関心を持った
自分のできないことが気になり落ち込んだ時、精神科の患者さんとかかわり、相手のできることを見つける精神科看護に関心を持った 脊髄損傷の人が災害時にどうしているかをテーマに卒業論文に取り組んだ。自分の不安や困難を突き詰め対策を考えるのは楽しかった
脊髄損傷の人が災害時にどうしているかをテーマに卒業論文に取り組んだ。自分の不安や困難を突き詰め対策を考えるのは楽しかった