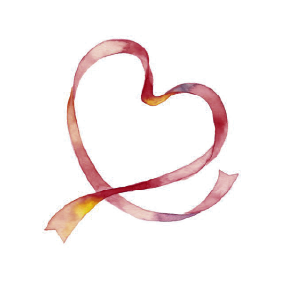※写真をクリックすると、動画の再生が始まります。
インタビュー時年齢:25歳(2018年12月)
障害の内容:聴覚障害(ろう)
学校と専攻:大学・看護学(2011年度入学)、大学院(2015年度入学)
関東地方在住の女性。生まれつきのろうで、両親もろうの家に育った。中学2年生の時に看護師になりたいと思い、看護大学に進学した。大学では、ノートテイクや手話通訳のサポートを得ながら講義や演習、実習をこなし、看護師の国家資格を得た。その後大学院に進学し、ろうの利用者が集まる施設で看護職として働いたり、ろう団体から依頼されて講演活動などをしている。
語りの内容
患者さんの安全を守る、命を守るということが大事ですよね。もうすごい責任は重大なので、私にはできないんじゃないかってすごいショックだったことを覚えています…。
コミュニケーション、実際の会話について、言っていることが分からないということももちろんなんですが、どうやったらきちんと患者さんと信頼し合えるか、安全を守れるか、自分にできることは何だろうということをすごく悩んだ時期がありました……。
実際、音とか音声とかが多いですよね。病院の中は。いろいろ音で知らせてくれますよね。ナースコールで呼ぶとか、ベッドコールとか、(ベッドから)下りちゃったら何かが鳴るとか。
この患者さんもベッドコールを使っていて、ベッドの下に下りたら音が鳴るようにはなっていたんですけれども、私は聞こえず、ベッドコールとナースコールの音が違うという判断もできないし。
実際は通訳が一緒にいたので聞いていて、「あ、今鳴ったよ」って教えてくれたんですけれども、自分でそれを解決できないのは自分で責任が持てないのではないかということを思って。自分の限界を知ることができて良かったなと思います。
でもそれを解決するためにはどうしたらいいんだろうっていうことに答えがなかなか見つからず、苦しい時期もありました。
で もその経験、2年の最後の実習の経験があって3年になってから、悩んでいたんですけど、やっぱり看護を続けようって決めました。
それ以降はさらに注意しました。本当にここで待っていてください、お願いします、帰るまではそこでずっと座っててねって2回も3回も同じことを何回も確認して気を付けるように変わった自分がいます。
患 者さんとのコミュニケーションで聞こえないから無理っていうのは嫌だったので、きちっと把握したいと思っていました。
でも自分で補聴器とか口とかというだけではやっぱ限界があるんです、なので通訳に来てもらって患者さんの後ろに通訳に立ってもらって両方の顔が見えるようにして。
患者さんも、例えば手話通訳のほうばっかり私が見ていたら、患者さんもなんでこっち見ないんだろうと思って気持ちが伝わらないので。
とにかく手話通訳はちょっと大変だったのかなと思うんですけど、患者さんの後ろに(いてもらって)。とにかく患者さんと気持ちを伝え合うということを大切にしていきました…。