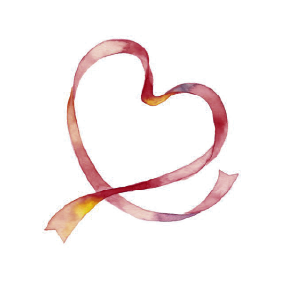学生時代の就職活動
例えば法学部や文学部を出ても法曹界の人や小説家になる人ばかりではないのですが、看護の場合は地域によって異なるものの看護を学んだ人の90%以上が看護職として就職します。2016年の障害者差別解消法施行以降日本では障害学生支援の考えは広まってきましたが、実際に障害のある人が看護職として働く一歩を踏み出すための就職活動では、障害が就職先選びに影響したり、壁に直面したことを話してくれた人がいました。
障害が影響した就職先選び
障害の有無にかかわらず看護学生の多くにとって、卒業後にどのような就職先を選択するかは、大きな意思決定です。なかでも障害のある看護学生では、就職先選びに自分の障害が影響することがあります。しかしそれは決してネガティブな影響の仕方ばかりではありません。障害があるがゆえの気づきや、熱意をもって就職先を選択したと話した人たちがいました。
内部障害と聴覚障害のある人は、実習で自信をなくしかけていた時に訪れた精神科実習での患者とのかかわり方を自分自身の境遇と重ね合わせて、進路を選択したと話していました(「障害があり看護を学ぶということ」のインタビュー19を参照)。
またその後は、実習での体験も生かして就職活動をしていきました。
また高校生の時にクローン病と診断された人は、入院中の体験から看護師を目指そうと思い、その時から自分が入院していた病棟で働きたいという思いを就職活動でも貫いたという話をしていました。
一方で障害があるために定期的な治療が必要で、それが就職先の選択に影響した人がいます。週に3回の透析治療が必要な内部障害の人は、就職に際して、まずは透析施設を先に探したと話していました。
障害の伝え方
自分の仕事を決めるための就職活動には様々な不安が伴います。障害者雇用促進法により、医療機関は障害のある看護師(看護学生)の受け入れを促進する必要がありますが、障害のある看護学生は自分の障害について何をどのように伝えて、どう反応されるかということに不安を抱く人がいました。
障害のことを伝えるか否かは、その障害が外から気づかれやすいかどうかにも影響します。
(障害を周囲へどう伝えるかは、「学校・職場での障害の開示」もご覧ください。)
内部障害と聴覚障害のある人は、就職活動用の書類に健康状態を書く欄があったため担任の先生に相談をして、伝え方を事前に考えたという話をしていました。
障害を開示して面接を受けると、障害があって看護師の仕事ができるか?と聞かれてしまうことが多くあるようです。しかし特に新卒採用の場合は看護職としての通常業務の経験もないため、障害があってどのように働くかということには、やってみないと分からないとしか答えられません。
例えば前述の内部障害と聴覚障害のある人は、面談の際に夜勤ができそうかと聞かれて、やったことがないので分からないと答えています。
障害があってどう働くのか(働けないのではないか)ということや、障害があることで夜勤ができるか(できないのではないか)と尋ねる質問自体が、場合によって障害のある人を歓迎していない態度の表れになってしまいますし、障害のある人にとっては社会的な障壁※になり得ます。
※「社会的障壁」とは、障害のある人がそれにより相当な制限を受ける、多数派向けの①社会における事物、②制度、③慣行や文化、④観念や偏見 の一切のものを言います。
障害があり看護職として就職することを決めた人の中には、障害を積極的に開示して、障害を味方につけて就職活動をした人もいます。
高校生の時にクローン病と診断された人は、面接ではクローン病になったから看護師になりたいと思ったことをしっかり伝えたそうです。
また障害が外から気づかれやすい車椅子ユーザーの人も、実際に自分には何ができて何ができないかは自分自身で説明するしかありません。次の方は、まずは自分ができないことを正直に伝えたうえで、できることややりたいことを伝えていました。
直面した壁
障害のある医療者からは、在学中に教育機関では十分な配慮や支援を得られたにもかかわらず、就職活動において壁に直面したという話がよく聞かれます。学費を支払って学ぶ学生の立場と、組織に雇用される職員の立場では根拠となる法律や制度が異なりますが、障害のない学生と同等にという意味では、教育から就業へのシームレスな移行は今後の課題と言えます。
実習中、手話通訳を付けて学んでいた聴覚障害の人は、手話通訳を付けて就職するということについて大きな壁があったことを話していました。
また透析をしながら看護学生として学んでいた人は、透析は恥ずかしいことではないため正直に履歴書に書いていたら、就職活動の面接で驚くような言葉を投げかけられた話をしています。
その後、この方は5つ目の採用面接試験の場で看護部長から「あなたが透析していることが、患者に関係あるのか?」と言われて、これまで準備してきた志望動機などを初めて聞かれ、採用された話をしています(こちらを参照)。
また高次脳機能障害の症状のある人は、採用側ではなく教育機関側の教員に、免許は取れても看護師は難しいと言われたことを話していました。
なぜそういった発言が聞かれるかを考えると、医療現場では目の前にいる患者の安全が優先されるという話が出てきます。確かに中には患者の生命に直結する緊急時の対応が求められる現場もあり、高度な技術が求められることもあります。しかし実際に看護職が働く現場は急性期の病棟から療養病棟、外来、訪問看護など非常に多様です。業務内容も、患者に直接針を刺すような処置を行うため一定の技術が求められる場面もあれば、相談業務のみのところもあります。つまりその人が働けるかどうかは、環境によると言えます。
また看護師免許を取る前の基礎教育課程の実習が急性期病院や病棟中心で、新卒は急性期や病棟で働くことが慣習とされていることも、多様な人の多様な働き方を推進する障壁となっている可能性があります。さらに、教育機関側や採用側の言葉は、本人が苦労するからという親切心からのものかもしれません。
いずれにしても、本人が自分の進路を納得して選択できるようなかかわりが教育機関などには求められています。
さらに面接そのものではないですが、車椅子ユーザーの人は、就職の合同説明会に行ったときの自分を見る目が気になったという話をしていました。
多数派向けの態度なども、障害のある人にとっては社会参加を阻む「障壁」の一つと言われていますが、多数派が意識しにくい「態度」などをどのように変えていくかは、今後の大きな課題と言えるかもしれません。
2025年3月公開
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。

 実習が印象深く、就職先に精神科を選んだ。教員に相談してゆったり落ち着いて働ける場所を教えてもらいインターンシップに行った
実習が印象深く、就職先に精神科を選んだ。教員に相談してゆったり落ち着いて働ける場所を教えてもらいインターンシップに行った 高校生で入院した体験から看護師を目指し、その入院病棟に就職したいと思って就職活動を行った。思いがぶれることはなかった
高校生で入院した体験から看護師を目指し、その入院病棟に就職したいと思って就職活動を行った。思いがぶれることはなかった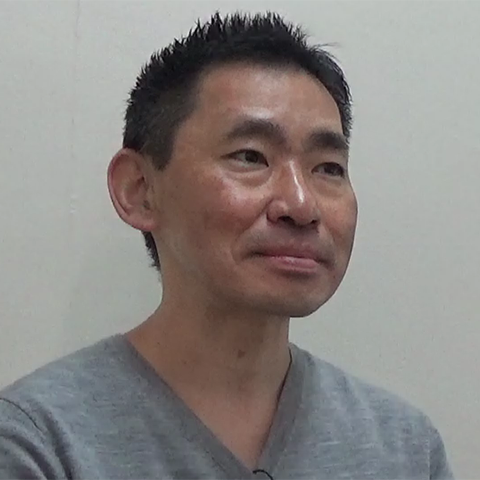 就職先は、就職したい病院よりも前にまず夕方6時からの夜間透析が行える施設を探し、そこを中心に就職できる病院を探していった
就職先は、就職したい病院よりも前にまず夕方6時からの夜間透析が行える施設を探し、そこを中心に就職できる病院を探していった 面接では移乗や体位変換はできないが観察スキルや知識は活かせると伝えた。看護職にこだわらないと言ったが看護職で採用された
面接では移乗や体位変換はできないが観察スキルや知識は活かせると伝えた。看護職にこだわらないと言ったが看護職で採用された 病院で働きたくて手話通訳を付けてインターンシップへ行ったところ、通訳に依存していては仕事はできないと言われた(手話)
病院で働きたくて手話通訳を付けてインターンシップへ行ったところ、通訳に依存していては仕事はできないと言われた(手話)