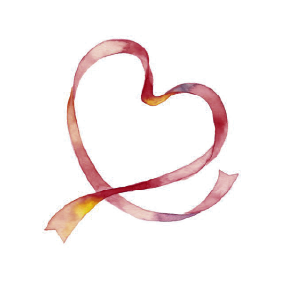※写真をクリックすると、動画の再生が始まります。
インタビュー時年齢:25歳(2018年12月)
障害の内容:聴覚障害(ろう)
学校と専攻:大学・看護学(2011年度入学)、大学院(2015年度入学)
関東地方在住の女性。生まれつきのろうで、両親もろうの家に育った。中学2年生の時に看護師になりたいと思い、看護大学に進学した。大学では、ノートテイクや手話通訳のサポートを得ながら講義や演習、実習をこなし、看護師の国家資格を得た。その後大学院に進学し、ろうの利用者が集まる施設で看護職として働いたり、ろう団体から依頼されて講演活動などをしている。
語りの内容
実習、3年の最後になって、病院の看護師っていうのも見て、ああ、こんな感じだなっていうことが、もう大体想像ができるようになり…、実際に自分も病院で働きたいなっていう思いもありました。とにかく、入った後、患者さんとのコミュニケーションをどうするのか、どうしようっていうことは答えは見つからない、見つかったわけではないんですけれども病院で働きたいなという気持ちはありました。
なので、いろんな病院にインターンで、春休みとか多いんですけど3~4回ぐらいは行ったんですが、実習のときも手話通訳を頼んで一緒に行きました…。
そのときは自分で払ったのかな。ちょっと覚えていない(以下、本人補足:「(よくよく思い出したら、インターンシップの通訳の費用も大学が出してくれていました)」)んですけれども、インターンはもし何かあったときに責任は誰がっていうのもあり、コミュニケーションを取れないので通訳を頼んで一緒に行きました。
病院からは「手話通訳に依存しているようじゃ仕事はできないでしょう」みたいなことを言われたことが何度かありました。確かにそうだよな。病院にもし入っても手話通訳の費用は誰が払うんだ、自分で払うのも難しいし病院側も、病院では出しません。
でも手話通訳がいないと実際に患者さんときちんとコミュニケーションの自信がなかったので、とにかく何回か、4つ、5つの病院に行って話をしました。
例えば急性期とか、救急とかは、もう本当にその場の判断とコミュニケーションが必要なので、ちょっとそれは自分には合わないんだっていうことが分かりました。
それで慢性期病棟とかゆっくり対応ができる、患者さんとお話をできて信頼関係を結べる、その後その患者さんとのコミュニケーション方法を見つければいいかなと思いました。
なので慢性期(病棟)がいいなという話をして、でもやっぱり病院としては難しいと思うと言われました。もう毎日泣いていたんですけれども、それが現実なんだなということを知りました。
そのときにたまたま同級生に、もし自分が病院に働いて偉くなって看護部長になったら私のことを採用するからみたいに友達が言ってくれて、もうとてもうれしかったです。
もちろんコミュニケーション難しい面もある、課題もたくさんあるんですけれども、同級生は「でもべつに問題ないんじゃない」って思ってくれるっていうことが本当にうれしかったです。
でも、現実の社会はやっぱり難しいんだなということが分かりました。結局病院で働くっていうことがなかなか難しいなということが分かって、
研究にも興味があったので、特に聴覚障害者の医療との関わりとか、
健康に関するいろんな情報とか、社会ではテレビとか普通に皆さん、世間話の中にも情報って本当にたくさんあるんですけど、
ろう者や難聴者はなかなかその情報の限界があるので、その辺の研究をしたいという気持ちもあって、大学院に進もうということに決めました。