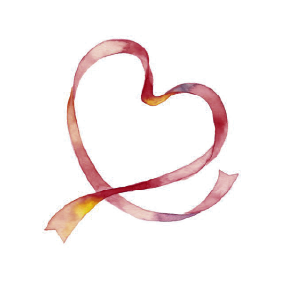職場での環境調整や配慮
障害のある人と共に働く社会を目指した法律である障害者雇用促進法は、日本が国連の障害者権利条約への批准を目指した国内の体制整備の一貫として、2013年に改正されました。そこで職場における障害がある人への合理的配慮の提供が定められています。実際に病いや障害のある看護職が働くにあたっては、様々な環境調整や部署ごとの配慮などが行われてきました。
もちろん障害のための困りごとは、その人自身の機能障害とその人がいる環境の関係性によって決まってくるので一人一人異なります。ここではどのような環境調整や配慮があれば働き続けられるのか、具体的な経験を紹介します。
就職時の障害や配慮に関する相談
働くうえで何らかの配慮を必要とする際、自分の障害や困りごと、今後心配なことを伝えて配慮を求めるという手順を踏みます。大学ではそういった申請の窓口を障害学生支援室や学生課などが担うことが一般的ですが、職場の場合は直属の上司や看護部長などに直接伝えて、(合理的)配慮を検討するということが多いようです。
入職時すでに障害が分かっていた人は、診断書を提出したり、障害や病気について管理者に伝えたりしていました。ただ具体的に本人の意向を聞かれるかどうかは、職場によって異なるようです。
次のクローン病の人は、就職活動の際に診断書の提出はしていたが、特にその後病気について聞かれることもなく、配慮も必要なかったので伝えていなかったと話していました。
高次脳機能障害の人は、入職時に看護部長には障害のことを伝えたけれど、それが直属の上司である師長に伝わっていたか分からず、そういった情報共有のあり方に問題意識を持っていました。
学生の時に線維筋痛症と診断された人は、入職してすぐに師長と面談をした際に自分の病気について伝え、どこまで情報共有して良いか確認されたことを話しています。
また聴覚障害と内部障害の人は、直属の上司に障害について伝えたところ、やってみてその都度相談してほしいと声をかけられていました。
また相談先は就職先だけに限りません。
これまでにいくつかの職場を経験してきた精神障害と発達障害のある人は、現在の職場に就職した際、地域の就労定着支援サービスを利用して職場を探し、サービスを利用しながら働き続けていることを話していました。
復職時の働き方に関する相談
就職した時には障害や病気がなかった人が就職中に何らかの障害をもち、休職を経ておなじ職場に復職することもあります。
今回職場復帰について話をした人は、いずれも自分の職場で治療を受けた経験があり、その後の働き方について同僚でもある主治医や上司と細やかな相談をしていました。
入職後の1年目で骨肉腫のために骨盤の手術をし、車いすを利用しながら職場復帰を目指していた人は、主治医や看護師長などと相談をしたことを話していました。
脊椎に膿が溜まる脊髄膿瘍で同じく車椅子を使うようになった人も、入院中に看護師として戻りたいという思いを主治医に伝えたときのことを話していました。
この方は復帰後の職場として放射線科のRI室が選ばれています。学生時代は、母性看護や高齢者看護、在学看護など、環境が異なる全ての看護領域を短期間で回る必要がありますが、職場の場合、一つの部署で必要とされる業務は限定的です。ひとつの病院の中でも、その人の特性に合わせて働きやすい場所を調整していくことが可能と言えます。
胃がんの治療後に職場復帰を希望した人は、半日から働き始めたいと上司に相談した時のことを話しています。
具体的な配慮の内容
法律に基づいた「合理的配慮」は、組織が一貫した姿勢で行うものですが、実際の障害のある人に対する配慮には、その部署や個人的な配慮など、様々なものがあります。
障害における困りごとは、その人の機能障害と社会の環境や制度との関係性によって大きく変わるので、配慮の内容も人によって様々です。
今回インタビューに答えた人では、障害があっても配慮が不要だった人もいれば、「部署の配置や役割の調整」、「勤務体制やステップアップのタイミングの調整」、「休みの調整」、「夜勤やオンコール」のこと、「管理職にまつわる調整」と様々な調整や配慮が行われていました。
配慮が不要だった
障害があっても特定の配慮を必要としない人は多くいます。1型糖尿病の方は、周囲には伝えていたが特に職場で調整していたことは何もなかったことを話していました。
うつ病があることを伝えたうえで就職した人も特に病院から配慮はなく、自分で仮眠をとるなどして工夫をしていたと話していました。
役割の調整
病棟の看護師は複数人のチームで働きますが、チームメンバーには、特定の役割が割り振られることがあります。障害がある看護職の人たちは、それぞれ柔軟にチーム内の役割や配置の調整を受けながら働いていました。
就職して数年後の20代後半で難病のベーチェット病と診断された人は、診断がついて復帰した後は、夜勤やリーダーの回数を減らしてもらったことを話していました。
勤務体制やステップアップのタイミングの調整
多くの病院や病棟では、新人として入職した1年目から何か月かすると担当患者を持つことや夜勤を開始することなど、ステップアップをしていきながら、1人前になっていきます。通常ステップアップのスケジュールには標準的なものが準備されていますが、障害や病気のために個別のステップアップの過程をたどっている人もいます。
入職時に線維筋痛症があることを伝えていた人は、病棟を2つのチームに分けてそれぞれを担当するチーム制の看護体制のなか、自分は重症者が少ない患者を担当するチームに振り分けられていることが多かったということを話していました。また、夜勤が増えるタイミングを緩やかにしてもらうなど、大きく制限するのではなく、自分の今後のことも考えてくれる師長の言動についても話しています。
他にも、骨肉腫の手術後に車椅子で職場復帰をした人は、勤務時間に関して、最初短時間勤務から始めて徐々にフルタイムに戻していき、業務内容も職場と一緒に考えていったと話していました。
同じく休職後に車椅子で復職した人は、復職後4年間はリハビリをしながら勤務するという勤務体制を認めてもらっていたことを話していました。給与に関しても、100%ではないけれど、8割程度の支給から始められたとのことです。
休みの調整
内部障害などが何らかの慢性的な疾患の場合、定期的に受診が必要な人もいます。受診をするためには休みが必要ですが、休みを取りやすくしてくれる配慮があったと話した人もいました。
線維筋痛症の人は、休み希望が通りやすかった職場について話しています。配慮は個人の状態に合わせて個別に行われるものですが、配慮をせずともみんなが働きやすいユニバーサルデザインの考え方も、様々な人がともに働く社会では重要です。
夜勤やオンコール
看護師の働き方の特徴として夜勤やオンコール(臨時の呼び出しのための待機)があります。本来なら寝ている時間に働くことや、臨時で呼び出される働き方は、日中だけの規則的な働き方よりも負荷が高いものです。ただ夜勤やオンコールには手当があるため、経済的なメリットが大きい働き方でもあります。
今回のインタビューでも、複数の人が夜勤やオンコールに関することを話していました。
骨肉腫の手術後に車椅子で職場復帰をした人は、その後同じ病棟で6年間働き続けたが、その間、夜勤はせず、日勤だけの働き方をしていました。
また胃がんの治療後に同じ病院に復帰をした人は、当初夜勤ができると思って復帰したが再発して思い通りにはいかなかったものの、オンコールで働けて良かったことを話していました。
また職場での配慮ではないですが、精神障害と発達障害のある人はもともと夜勤がない看護職の仕事を選んで、オンコール対応をしていることを話していました。
管理職にまつわる調整
一般企業でも同じですが、管理職は経験を積んだ人が就く役職です。管理職になると部下に対しての管理責任が発生し、業務量が多くなったり、質も変わります。病気や障害を経験した人の中には、管理職としての働き方に調整が必要だった人もいました。
胃がんの治療後に復職した人は、その後、肺に影が見つかり治療を行うために2回目の休職をしました。その後の復帰では、日勤のみの仕事に変わり、管理職を降りたときの気持ちを次のように話していました。
また持病のてんかんを服薬でコントロールしながら仕事を続けていた人は、50代で看護部長をしていた時に多忙を極め、仕事自体は楽しかったが徐々に眠れなくなって、部長職を降りたことを話しています。その後うつ病と診断されましたが、うまく休めないでいた時にかけられた言葉を、今自分が管理職として人に伝えていると言います。
周囲への依頼やチームワーク
障害の有無にかかわらず、複数の人が一緒に働くためには、お互いに持ちつ持たれつの関係性が重要です。職場からの「配慮」とは別に、こうするとできるからお願いしたいと個人的に要望を伝えたり、自然と周囲が自分の苦手をカバーしてくれた体験を話した人がいました。
車椅子を利用していると、自分の足置きが邪魔になって、ものに近寄れないということがあります。そういった自分ができないことに関して、周囲のスタッフが素早く手伝ってくれていたことを話した人がいました。
また産業看護師として企業で働いている聴覚障害のある人は、コロナでオンラインアプリを多く使うようになったときに、音声だけでなく文章で送ってもらうように依頼していたと言います。
この人はコロナ禍でチャットを使うようになったことが良かったと話しており、環境を調整する大切さを感じます。
2025年3月公開
認定 NPO 法人「健康と病いの語りディペックス・ジャパン」では、一緒に活動をしてくださる方
寄付という形で活動をご支援くださる方を常時大募集しています。

 就職時に診断書は提出していたが、入職してからは症状も落ち着いており、心配することもなかったので特に職場には伝えなかった
就職時に診断書は提出していたが、入職してからは症状も落ち着いており、心配することもなかったので特に職場には伝えなかった 入職後、直属の上司に難聴と体力のことを伝えた。夜勤は少しずつ様子をみてしんどかったらその都度相談してほしいと言われた
入職後、直属の上司に難聴と体力のことを伝えた。夜勤は少しずつ様子をみてしんどかったらその都度相談してほしいと言われた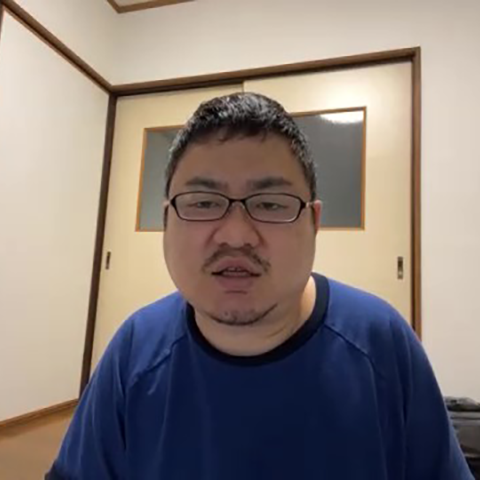 転職に際して公的な就労定着支援サービスを利用した。就職先を相談したり、面接についてきてくれたりした(次のクリップへ続く)
転職に際して公的な就労定着支援サービスを利用した。就職先を相談したり、面接についてきてくれたりした(次のクリップへ続く) 治療後は体力が落ちて復職できるか不安な時期もあったが、病気で諦めるのは悔しい思いもあり、周囲と相談しながら復職を目指した
治療後は体力が落ちて復職できるか不安な時期もあったが、病気で諦めるのは悔しい思いもあり、周囲と相談しながら復職を目指した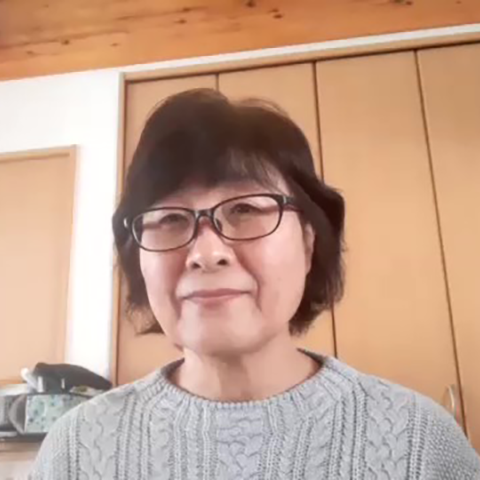 看護師として復帰したいと主治医に強く伝えたら、院長と話し合って復帰する職場として車椅子でバリアが少ない職場を選んでくれた
看護師として復帰したいと主治医に強く伝えたら、院長と話し合って復帰する職場として車椅子でバリアが少ない職場を選んでくれた 胃の手術後食事の調整が必要で復職は不安だったが、半日勤務からはじめて、半年くらいかけて周囲と同じシフトに戻してもらった
胃の手術後食事の調整が必要で復職は不安だったが、半日勤務からはじめて、半年くらいかけて周囲と同じシフトに戻してもらった 職場には病気のことは伝えており、倒れたらお願いということは言ってあったが、だから何かしてほしいということはなかった
職場には病気のことは伝えており、倒れたらお願いということは言ってあったが、だから何かしてほしいということはなかった 多忙を極めこのままでは自分がうつ病になると思い部長職を降りた。てんかんの薬をもらいに行った先でうつ病と診断された
多忙を極めこのままでは自分がうつ病になると思い部長職を降りた。てんかんの薬をもらいに行った先でうつ病と診断された